
今回は、日本企業に勤務する蘇さんにお話を伺った。蘇さんは、日本企業の中国現地法人勤務から数えて、足かけ6年半も日本企業に勤務されている。中国の人がどのようにして日本企業に溶け込んでいるか、溶け込めない人はどこに問題があるのか、現役の会社員ならでは、のリアルなご意見を伺うことが出来た。
蘇さんの観察力は鋭い。蘇さんのように、違う文化や環境を冷静に比較できる「ブリッジ」の役割を担ってくれる人が増えれば、中日両国にプラスになるに違いない。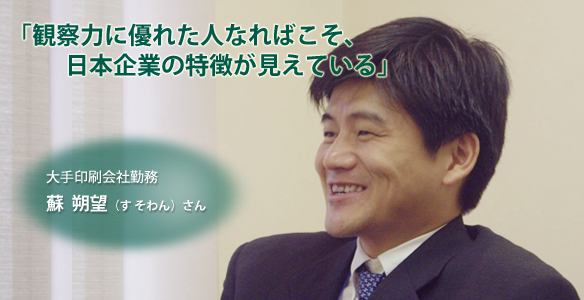
蘇 朔望 プロファイル
中国・上海出身、国鉄の専門学校を経て、上海鉄道局に勤務。外資系企業への勤務を希望し、日本のオーディオ・家電メーカーの上海現地法人に転職。その後1998年に来日。神戸のYMCAで日本語を学習し、1999年に慶応義塾大学の総合政策学部に入学。学生時代でのアルバイトがきっかけで、卒業と同時に大手印刷会社に入社。Eビジネス事業部、情報ビジネス事業部などを経て、現在、国際本部 国際部に勤務。日中の架け橋として活躍中。
蘇さんの観察力は鋭い。蘇さんのように、違う文化や環境を冷静に比較できる「ブリッジ」の役割を担ってくれる人が増えれば、中日両国にプラスになるに違いない。
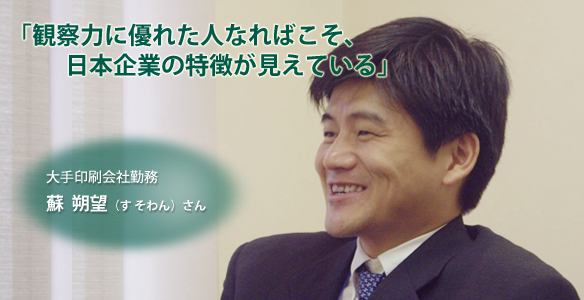
蘇 朔望 プロファイル
中国・上海出身、国鉄の専門学校を経て、上海鉄道局に勤務。外資系企業への勤務を希望し、日本のオーディオ・家電メーカーの上海現地法人に転職。その後1998年に来日。神戸のYMCAで日本語を学習し、1999年に慶応義塾大学の総合政策学部に入学。学生時代でのアルバイトがきっかけで、卒業と同時に大手印刷会社に入社。Eビジネス事業部、情報ビジネス事業部などを経て、現在、国際本部 国際部に勤務。日中の架け橋として活躍中。
● 安定した国営企業に飽き足らず、民間へ。そして日本へ。
—ダイジョブ「まず、現在に至るまでのご経歴を伺わせてください。」
父が鉄道マンだったものですから、私も鉄道専門学校を卒業して国営の上海鉄道局に勤務しました。当時の中国では、鉄道はすべて国営ですから、身分としては公務員ですね。国営鉄道では、ディーゼルエンジンの発電システム・車両空調の運用などに従事していたのですが、2年ほど経った頃、「国営以外の会社で働いてみたい」という気持ちが強くなり、人材バンクに登録しました。それがきっかけで、日本のオーディオ・家電メーカーの上海現地法人に転職しました。そこでは、企画と販促を中心に、営業に関する評価制度、税務など何でもやりましたが、2年半ほど勤めて、日本へ留学しました。
—ダイジョブ「何故、転職先に日本企業を選ばれたのですか?」
漢字や人種など、中国と似ているものが多いことと、日本の技術はすばらしいものだと思っていたことから、日本企業を選択しました。
—ダイジョブ「その後、日本に留学されたのですよね? 日本に来られた理由を教えてください。」
当時の上司が、「海外に出てみろ」と助言してくれましたし、私も日本の企業をより深く知るには、日本に行った方が良いと思いました。そこで1998年に来日し、まず、神戸の日本語学校で半年間学び、日本語検定1級と、留学生向けのセンター試験を受けました。
—ダイジョブ「来日半年後の1999年には大学入学されていますが、日本語での受験は難しくありませんでしたか?」
中国で日本企業に勤務していた時に、日本語を話す方は問題なくなっていましたが、「カタカナ」が難しかったですね。センター試験は「世界史」で受けたのですが、中国にはそもそも「カタカナ」が無い上、人物名のカタカナ表記が中国語での発音と違うので、1ヶ月は集中して世界史に出る人物名と王朝名のカタカナの読み方の勉強にあけくれました。勉強の甲斐があって、センター試験でも比較的高い点数を取ることができたので、慶応義塾大学に入ることができました。他の大学にも願書を提出しましたが、日本行きを勧めてくれた上司が慶応義塾大学出身だったこと、湘南藤沢キャンパスの環境が良かったこともあって、慶応義塾大学に入学を決めました。学部は、「総合政策学部」で、ファイナンスを中心に勉強しました。
—ダイジョブ「大学時代は、どのような活動をされていたのですか?」
 大学1年〜2年の頃は日本語を習得し、3年目でパソコンなどの技能を身につけました。それから、大学の中国人留学生会の代表も務め、日中留学生の交流活動として、海や山での合宿、大学の文化祭への参加、他の大学との共同イベントなどをやりました。とても楽しかったですよ。そのほか、サービス業からSE業界まで、様々な業界でアルバイトをしてきました。学校とアルバイトを両立するのは大変でしたが、日本の社会を知り、日本の習慣を身につける点では、アルバイトから貴重な経験を得ることができました。大学生活を通して、日本社会に溶け込むための下準備が整いましたね。
大学1年〜2年の頃は日本語を習得し、3年目でパソコンなどの技能を身につけました。それから、大学の中国人留学生会の代表も務め、日中留学生の交流活動として、海や山での合宿、大学の文化祭への参加、他の大学との共同イベントなどをやりました。とても楽しかったですよ。そのほか、サービス業からSE業界まで、様々な業界でアルバイトをしてきました。学校とアルバイトを両立するのは大変でしたが、日本の社会を知り、日本の習慣を身につける点では、アルバイトから貴重な経験を得ることができました。大学生活を通して、日本社会に溶け込むための下準備が整いましたね。
—ダイジョブ「就職の時は、どのような活動をされました? 今の印刷会社は、就職活動をして入られたのですか?」
いいえ、大学3年の時から今の会社でアルバイトをしていたご縁で、2003年の卒業と同時に入社しました。
● 留学生が希望する卒業後の選択肢は、2つ。
—ダイジョブ「蘇さんご自身は日本企業に就職されましたが、一般的に、中国人留学生は、卒業後どうされるのでしょうね?」
留学生が希望する選択肢は、大きく分けて2通りだと思います。1つ目は、日本の大手企業で勤務する道、そして2つ目は、学者や研究員など学問を目指す道です。
1つ目の、日本の大手企業で勤務するケースでは、その後、さらに大きく2つの志向に分かれます。
(1) 中国関連の仕事を、本社または現地法人で行う
(2) 欧米などに行って、日本企業で蓄積した経験を活かせる仕事をする
ことです。
1つ目の、日本の大手企業で勤務するケースでは、その後、さらに大きく2つの志向に分かれます。
(1) 中国関連の仕事を、本社または現地法人で行う
(2) 欧米などに行って、日本企業で蓄積した経験を活かせる仕事をする
ことです。
—ダイジョブ「中国リターン・パターンと第3国へジャンプ・パターンですか。」
中国リターン・バターンには、本社社員としての駐在と直接現地での雇用との2種類があります。仕事の内容や待遇面、勤務地などいろいろな状況を比較して判断をしなければなりません。駐在員パターンの場合は、本社帰任後の仕事内容や勤務地などについて、日本企業のシステムに馴染まないケースがあると聞いています。中国にいる家族の問題、生活のし易さなど、環境面での違いもあるようです。
欧米企業に転職を図りたい場合も、いろいろな理由が考えられます。仕事の内容に満足できなかったり、日本企業とのミスマッチを感じることが、比較的多いように見えます。
欧米企業に転職を図りたい場合も、いろいろな理由が考えられます。仕事の内容に満足できなかったり、日本企業とのミスマッチを感じることが、比較的多いように見えます。
● ギャップを観察すると、システムの問題と心象の問題が浮かび上がる
—ダイジョブ「蘇さんは日本企業に勤務していらっしゃるので、今おっしゃったような中国の方と日本企業のギャップをある程度俯瞰してご覧になれると思います。どんな事を一番に感じていらっしゃいますか?」
まず、企業組織とその機能の違いがギャップの要因として挙げられると思います。日本の場合、事業部の下の各「課」同士が、部署を超えた連携を図る場合が多いですよね。それに比べ、以前の中国の国営企業の組織では、「課」は広い裁量権を持ち、独立性が強いものです。他の「課」との連携や協調姿勢は生まれにくいところがあります。どちらかと言えば、中国人は独立心が強いので、連携を強調する日本の企業組織に馴染めない人が多いようです。
—ダイジョブ「そうですね。日本の社員は、公式・非公式を問わず、他部署との連絡はよく取り合っていますよね。オペレーションの遂行機能を担っているイメージです。」
 次に、最近の若い中国人は、「一人っ子政策」で兄弟姉妹がいないために、「協調」のトレーニングがあまりなされてない、と思いますね。1979年以降に一人っ子として生まれた中国人は、十分な教育投資を受け、パソコンのスキルや英語など、技術力・知識は向上しましたが、「協調性」に欠けているところがあるかも知れません。
次に、最近の若い中国人は、「一人っ子政策」で兄弟姉妹がいないために、「協調」のトレーニングがあまりなされてない、と思いますね。1979年以降に一人っ子として生まれた中国人は、十分な教育投資を受け、パソコンのスキルや英語など、技術力・知識は向上しましたが、「協調性」に欠けているところがあるかも知れません。また、多くの中国人は、日本について、両親から聞いた話や、若い留学生の眼を通して見た印象、中国での外資企業としての日本企業の姿しか知りません。一部のイメージで日本を捉えているため、実際に来日してイメージギャップが大きくなる、ということもあると思います。
—ダイジョブ「受け入れる日本の企業側も、そういった事情を知らないといけませんね。」
会社に対する印象はだいたい3ヶ月で固まりますので、新入社員に対する「入り口での教育」は重要です。企業側も、中国と日本を比較して説明するなど、両国の「違い」について、うまい説明をする工夫が必要でしょう。会社の人事部の負荷になりますが、入った直後のフォローに加え、入社前にきちんと説明する機会も多く設けていただきたいと願っています。
企業の採用担当者は、応募してきた中国人との「相性」を重視して、採用を決めるとよいと思います。「相性」は、履歴書から得た情報や面接などのコミュニケーションを通じて把握できると思うので、面接や説明会の機会を多くを設けることが、ミスマッチを防ぐポイントだと思います。
企業の採用担当者は、応募してきた中国人との「相性」を重視して、採用を決めるとよいと思います。「相性」は、履歴書から得た情報や面接などのコミュニケーションを通じて把握できると思うので、面接や説明会の機会を多くを設けることが、ミスマッチを防ぐポイントだと思います。
● 「目標=Goal」と「手段=専門性」を混同してはいけない。
—ダイジョブ「日本企業で働きたい中国の方へのアドバイスをいただけますか?」
 まず、「目標」と「手段」を混同しないように、と言いたいです。
まず、「目標」と「手段」を混同しないように、と言いたいです。目標とは「Goal」であり、手段は「専門性」です。本来は、『目標の達成』が重要で、専門性が高いことは、その実現手段でしかないはずです。ところが、「専門性」だけ追及する留学生が多いような気がします。
「目標=Goal」を達成するためには、他の知識やネットワークを持って組み立てることが必要です。日本の「ジョブ・ローテーション」の仕組みは、まさに、他部署の機能を熟知し、会社の目標を達成しやすくするためのものです。日本企業の多くは、個人の“専門性”だけで何かを達成できるような組織ではありません。その辺りを理解することは、日本企業に勤務する場合には重要なことだと思います。
それから次の3点です。
(1) 目標を明確に持つ・・・あいまいな目標でなく、なるべく明確な目標を持つ。
(2) 郷に入れば、郷に従え・・・少し自分の見方を抑えて、日本の国や日本企業のあり方を観察する。
(3) 私生活を含め、総合的に考える・・・結婚や生活の場など、将来の人生設計もする。
—ダイジョブ「留学生の方に限らず、日本人にも有益なアドバイスですね。」
目標が「短期」のものなのか、「長期」のものなのか、も重要です。設定期間により、達成する道筋は変わるはずですから。
—ダイジョブ「ところで、蘇さんご自身の今後の目標は?」
私自身の目標は、「日本と中国に関すること」と、「人と接する仕事」をベースに置きながら、日本が得意とする分野で日中双方にとってメリットのある仕事に従事し、少しなりとも両国の発展に貢献することです。
—ダイジョブ「どうもありがとうございました。」
| トップページへ戻る |

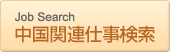
![[Daijob.com] メンバー登録](/images/ja/china/btn_china_register01.gif)
![[Daijob.com] メンバー登録について](/images/ja/china/arrow.gif)