
今回は、ブラウザのアドレスバーへの日本語入力検索サービスを提供する新進IT企業の「JWord」を創業された沈さんを取材した。沈さんは、26歳の時には既に3つの会社を興した経験を持つ方である。飛び級をして19歳で大学を卒業したのも異例なら、現在の会社JWordを創業仲間と2人で共同経営するスタイルも異例である。経歴を伺っていて感じたのは、「とにかく決断が速い」ことである。「中国人は決断が早いんです」とは、沈さんの言葉ではあるが、それにしても2〜3年周期で新しいことを始め、その決断はあっという間である。そろそろ日本にも飽きたのでは? と水を向けると、「今の会社を大きくするのが面白いので、日本を基盤にしていきたい」との答え。こんなユニークな才能のある方が、日本で頑張ってくれるとは、何ともうれしいことである。
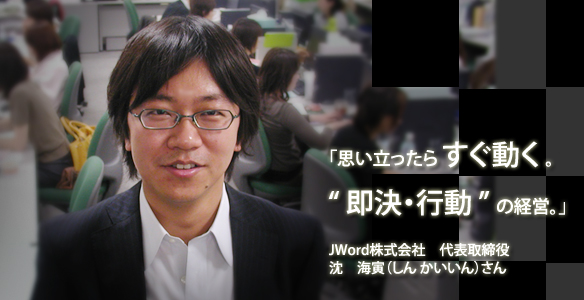
沈海寅 プロファイル
JWord株式会社 代表取締役社長。中国・上海出身。4歳で小学校に入学、飛び級により19歳で、電子情報工学及び管理工学の2学位で上海交通大学を卒業。上海デルファイ自動車エアコンシステム社にエンジニアとして勤務。1995年、21歳でエアコン測定機器の会社を共同設立し、IT事業部長に就任。1998年に来日し、中堅のシステム会社に勤務。2000年4月、株式会社インターパイロンを設立、代表取締役に就任。同じく2000年8月、現在の共同経営者である翁永飆(おう えいひょう)氏と共同で、株式会社アクセスポートを設立、翁氏とともに、代表取締役社長に就任。(株式会社アクセスポートは2005年4月JWord株式会社に社名変更。)
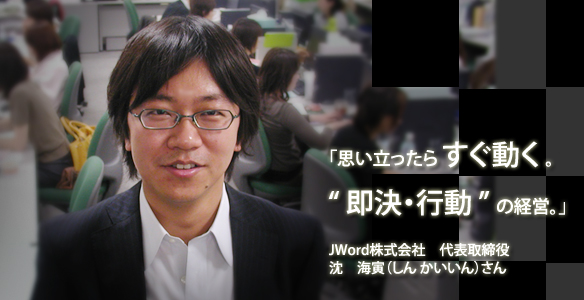
沈海寅 プロファイル
JWord株式会社 代表取締役社長。中国・上海出身。4歳で小学校に入学、飛び級により19歳で、電子情報工学及び管理工学の2学位で上海交通大学を卒業。上海デルファイ自動車エアコンシステム社にエンジニアとして勤務。1995年、21歳でエアコン測定機器の会社を共同設立し、IT事業部長に就任。1998年に来日し、中堅のシステム会社に勤務。2000年4月、株式会社インターパイロンを設立、代表取締役に就任。同じく2000年8月、現在の共同経営者である翁永飆(おう えいひょう)氏と共同で、株式会社アクセスポートを設立、翁氏とともに、代表取締役社長に就任。(株式会社アクセスポートは2005年4月JWord株式会社に社名変更。)
● 「海外に出る。」 決意してから2ヶ月で来日。
—ダイジョブ「沈さんは、大学を19歳でご卒業されたそうですね。大学を卒業されて、アメリカの自動車部品大手「上海デルファイ自動車エアコンシステム」に入られて、2年後の1995年には起業していらっしゃいます。その起業のいきさつを教えていただけますか?」
会社の取引先の人から誘われて、設立に参画しました。資本の参加はしていません。家電や車のエアコンメーカーがエアコンを開発する際の測定機器を作る「上海佐竹冷熱制御技術社」です。そこでIT事業部長に就任しました。当時はまだ、この分野はニッチ産業で、中国では発展していませんでした。今では大きな産業になっていますが、早期に参入したため、大きなシェアをとることが出来ました。
—ダイジョブ「会社は大きく発展していたのに、あっさりと辞めて、日本に来られた訳ですが、どういった理由ですか?」
確かに会社は大きくなり、良い待遇も受けていました。通常の大卒の7〜8倍のサラリーを得、住まいなどもそれなりでしたが、「おもしろさ」を感じなくなったんです。独身で若い内に海外へ行きたい、と思いました。特別に日本を希望していたのではありませんでした。アメリカと日本、シンガポール、カナダのVISAを申請していて、日本のVISAが一番早く取れたので、アメリカへの中継地のつもりで日本に来る事を決めました。
—ダイジョブ「日本での転職先のシステム会社は、来日してから探したのですか?」
いいえ、転職先を決めてから来日しました。応募先はインターネット検索を活用して中国に居ながら探しました。日本語は読めませんでしたが、日本語履歴書は友人に頼んで作ってもらい、漢字で当たりをつけて企業の採用ページから応募しました。応募したシステム会社の社長がたまたま旅行で上海に来るというので、英語で面接をしてもらい、即、内定をいただきました。海外に行くと決めてから日本に来るまで、2ヶ月くらいでしたね。
—ダイジョブ「そんなに短期間で実現したのですか。しつこいですが、せっかく興した会社で、おまけにIT事業部長という高い地位を手放すことに未練はありませんでしたか?」
僕は大学を19歳で卒業したので、24歳の時にはもう、5年間も社会人をやっていたわけです。同じ年の他の人は、会社勤めがせいぜい2年ですから、同年代の若い人とはちょっと違い、結構働いたな、という感じがありました。そろそろ違うことにチャレンジしたくなったんですね。
● 仕事の中に組み込めば、日本語学習も効率的。
—ダイジョブ「日本語の勉強はどうされました?」
仕事はDBやインターフェースの設計でしたが、自分としては簡単で早く終わるので、技術に関する日本語の書籍を読んでいました。その点は会社も理解があり、勉強することを薦めてくれました。来日時は、全く日本語が分からなかったのですが、半年でビジネス日本語ぐらいまでこなせるようになりました。
—ダイジョブ「ゼロから始めて、半年でビジネス日本語まで? Tipsを教えてください。読者も是非参考にしたいでしょう。」
そうですねぇ、仕事の時間を利用して本を読むことですか。私の場合は、その他、「毎日教科書を1時間読む」と決めて、1年間継続しました。あと、インターネットの「日本語教室」掲示板で日本語教師を目指している日本人女性と知り合い、週1回ぐらい会ってどこかへ案内してもらうなどして、遊びながら学んでいきました。
 —ダイジョブ「日本企業に勤める中国の方が困った事としてよく言うのが、「職場での日本人とのコミュニケーション」です。沈さんは困りませんでした? また、仕事での苦労はありませんでしたか?」
—ダイジョブ「日本企業に勤める中国の方が困った事としてよく言うのが、「職場での日本人とのコミュニケーション」です。沈さんは困りませんでした? また、仕事での苦労はありませんでしたか?」
中国にいた時から、日本人の取引相手と接したり、日本へ出張で来ていましたから、来日時に日本に対するイメージ・ギャップはありませんでした。また、会社には既に6人の中国人が勤務していましたので、日本人同僚も中国人に慣れていました。プログラムは英語主体ですから、とりたてて困ったと言う記憶は無いですね。
仕事自体は、すぐに覚えられました。日本語の勉強期間と思っていたので、与えられた仕事に不満はなく、空いた時間を他の人の手伝いをしたり、本やネットで日本語の勉強をするのに使って、日本語も上達しました。
仕事自体は、すぐに覚えられました。日本語の勉強期間と思っていたので、与えられた仕事に不満はなく、空いた時間を他の人の手伝いをしたり、本やネットで日本語の勉強をするのに使って、日本語も上達しました。
—ダイジョブ「生活で困ったことはありませんか? 住まいはどうしました?」
会社の中国人同僚が共同で借りていた家があり、たまたま一人が結婚して引っ越すので、その空いた部屋に入りました。言葉が分からないうちは、買い物など1人で行動する時には困ったこともあります。今では笑い話ですが、美容室で髪型について「××cmの短さ」など、長さの単位でしか説明できない。美容師さんもさぞ困ったでしょうね。(笑)
● 「日本で興した方が早い」 ドックイヤーを越える、スピードの決意から会社設立まで。(注1)
—ダイジョブ「JWordにつながる起業のきっかけは?」
1999年の秋に京都へ旅行に行き、郊外のホテルに泊まりました。近くのコンビニで何気なく「ネットランナー」という雑誌を買ってきましたら、たまたま「ベンチャー企業特集」で、インターネット関連のベンチャーを中心に100社の取材記事が掲載されていました。それまで、日本でもアメリカのシリコンバレーのように資金の直接調達が可能だとは思いませんでしたので、ベンチャー企業の事例を読んで、「日本でも起業できるのか。新たにアメリカで地盤を作ってから起業するのより、よっぽど早いじゃないか。」と思ったのです。
—ダイジョブ「1999年から2000年頃というと、IT系の若手ベンチャー起業家に資金が集まった頃ですね。渋谷が中心だったので、アメリカのシリコンバレーにあやかって『ビット・バレー』と呼ばれていました。具体的にはどんなアクションを起こされたのですか?」
 京都から戻って、11月に「ベッコアメ」というプロバイダーが主催していた、在日中国人向けの会合に出席しました。その会の出席者は11人ぐらいいましたが、その仲間から3社、会社が設立されていますよ。そこで初めて、共同設立者の翁と顔を会わせました。それまでは、中国のIT情報に関するメーリングリストで知り合ったメル友でしたが、会ったことはなかったんです。
京都から戻って、11月に「ベッコアメ」というプロバイダーが主催していた、在日中国人向けの会合に出席しました。その会の出席者は11人ぐらいいましたが、その仲間から3社、会社が設立されていますよ。そこで初めて、共同設立者の翁と顔を会わせました。それまでは、中国のIT情報に関するメーリングリストで知り合ったメル友でしたが、会ったことはなかったんです。
—ダイジョブ「翁さんとお二人で起業されたのですよね。」
ええ、11月に会合で会い、2000年の1月にはお互いをパートナーとして決め、ビジネス・モデルを立案しました。これには「2000年問題」が寄与しています。
—ダイジョブ「2000年問題というと、2000年になったとたん、コンピュータが一斉に誤作動を起こすのではないか? と、世界中で大騒ぎしたが、結局は大したことは起こらずソフトウェア業界がもうかった、というあれですね。それと何の関係が?」
システム会社に勤務中だったので、2000年問題対応のため、年末・年始は自宅待機していていました。時間があったので、3つのビジネス・プランのもとを立てたんです。3つの内の1つがJWordの日本展開のアイデアで、この技術は既に中国で事業化されていました。やはりIT関連のメーリングリストでその社長と知り合い、中国では彼が、日本では僕が日本語環境を開発して販売権を持つ、ということで合意しました。これが2月で、4月には、翁と合意して、インターパイロン社を作りました。資金は、半分が個人投資家、俗に言う“エンジェル”から調達し、残りの半分を翁と半々で持ちました。同じ年の8月には、インターパイロン社を親会社として、JWordの前身のアクセスポート社を興しました。(注2、注3)
—ダイジョブ「ちょっと整理させてください。ええと、1999年の秋に日本でのベンチャー起業を決意、11月にパートナーの翁さんと直接会い、1月から2月にかけてビジネス・モデルを立案、その内の1つがJWordの元になるネット技術で、中国のオリジナル開発者の合意を2月に取り、同じく2月には、個人投資家(エンジェル)の投資を受けて、翁さんと会社設立、8月には、JWord事業を専門に行う子会社を設立。」
ええ、そうです。
—ダイジョブ「すごいスピードですね。全部が1年以内、これはドッグ・イヤーどころではないですね。」
う〜〜ん。決めたらすぐ動くタイプなんですよね。(笑)
(注)
(注1)ドックイヤー:
(注2)2000年問題:
(注3)エンジェル:
 —ダイジョブ「バスや電車の待ち行列のことですね。来年に北京オリンピックを控えて、中国政府が必死に“マナー・キャンペーン”をしていますね。」
—ダイジョブ「バスや電車の待ち行列のことですね。来年に北京オリンピックを控えて、中国政府が必死に“マナー・キャンペーン”をしていますね。」
- 犬は人間の7倍の速さで年をとっていくことから、1年で通常の産業の7年分の変化がおきるIT業界の技術革新のスピードをこう呼んだ。近年は、もっとスピードが速くなり、1年で18年分の進歩をする「マウスイヤー」という言葉が使われている。
- 1960年代〜1980年代に開発されたプログラムは、下2桁で年号を表すことが多かったため、2000年を1900年とみなして誤作動が発生するのでは、と危惧され、世界中でプログラムの修正が行われた。2000年に年号が切り替わる前後には、多くのプログラマーがトラブル対応のため、待機していた。
- ベンチャー企業への資金提供と事業支援を行う個人投資家のこと。
● 中国文化と日本文化の違いは、「もの造り型」と「商業貿易型」の違いから。
—ダイジョブ「さて、本当はここからがこの取材のメインテーマなのですが(笑)、中国と日本の違い、そこから来る同胞、または日本企業へのアドバイスをいただけますか?」
中国は競争の激しい社会です。受験でも就職でも早く決断しないと負けてしまうので、スピーディに判断するのが国民性になっています。
決断が早いのは会社経営には良いことだと思います。反面、「順番待ちができない」という悪い点にもつながりますが(笑)。
決断が早いのは会社経営には良いことだと思います。反面、「順番待ちができない」という悪い点にもつながりますが(笑)。
 —ダイジョブ「バスや電車の待ち行列のことですね。来年に北京オリンピックを控えて、中国政府が必死に“マナー・キャンペーン”をしていますね。」
—ダイジョブ「バスや電車の待ち行列のことですね。来年に北京オリンピックを控えて、中国政府が必死に“マナー・キャンペーン”をしていますね。」
僕は、その違いは、文化の型の違いから来るものだと思います。例えば、時間感覚で言うと、日本人は「悠長」、中国人は「スピーディ」、東南アジアの他の国は「ゆっくり」という違いがありますね。その違いも文化の型から来ていると思うんです。
日本文化の基礎になるのは、「もの造り」なので、開発に時間がかかります。だから時間の感覚も長くなります。
一方、中国文化の基礎は「商業貿易」で、商いの感覚が基礎になっていると思うんですね。短期間でリターンを求める傾向があり、スピードが重視されます。
日本文化の基礎になるのは、「もの造り」なので、開発に時間がかかります。だから時間の感覚も長くなります。
一方、中国文化の基礎は「商業貿易」で、商いの感覚が基礎になっていると思うんですね。短期間でリターンを求める傾向があり、スピードが重視されます。
—ダイジョブ「なるほど、それは興味深い視点ですね。かなり納得できる見方です。他には?」
日本に来ている中国人は、「能力が高い」+「経験などで苦労している」人達です。自分の能力より低い仕事を割り振られるとプライドが傷つきますし、単調な仕事は飽きてしまいます。企業担当者、特に現場の上司は、中国人の部下にはチャレンジできる仕事を与えて、やる気を促した方がよいと思います。「入るのは会社。辞めるのは部署」という言葉もありますから。同時に、中国の人は、能力を認められる機会を自分から掴むようなアプローチをするように、心がけるべきですね。
—ダイジョブ「どうもありがとうございました。」
(注)取材日 2 月 22 日。沈社長はこの後、3 月 27 日に JWord株式会社の取締役を退き、ACCESSPORT 株式会社の代表取締役に就任しておられます。
| トップページへ戻る |

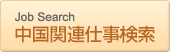
![[Daijob.com] メンバー登録](/images/ja/china/btn_china_register01.gif)
![[Daijob.com] メンバー登録について](/images/ja/china/arrow.gif)