Global Career Guide


- 外資系転職求人 Daijob.com TOP
- Global Career Guide
- タカシの外資系物語
- 英語で “デザイン・シンキング” しよう!(その3)
英語で “デザイン・シンキング” しよう!(その3)

宿題、やりましたか?!
(前回の続き)製品・サービスの新しい開発技法である “デザイン・シンキング”。英語で開催される社内トレーニングにエントリーされたタカシは、グローバル最先端の技法を学べることに有頂天になりつつも、久々の英語にて実施されるセミナーについていけるかどうか、一抹の不安をかかえながら、当日を迎えたのでした・・・
まずは、前回の宿題から始めましょう。以下に、私の回答を例示しておきます。
- ● 宿題 = 最近、自身が気に入っている/気になっている製品・サービスを1つ選んで、以下の項目を埋める ※ただし、できる限り文字ではなく、絵や写真で表現すること
- ● 回答項目
✔ 製品・サービス名 ・・・ Evernote シリーズの「Scannable」※スマホのカメラ機能を使って、紙データをスキャンするアプリ
✔ 魅力を感じる点 ・・・ ペーパーレス、操作が少ない・なめらか、free(無料)
✔ どのような “体験” がその製品・サービスを魅力的にしているか ・・・ 操作にストレスを感じない、easy
✔ 他人に勧めたくなるポイント ・・・ スキャンした文書がきれい、stylish、smart
✔ 上記の詳細な “説明”
(証拠1) レシートの形式を自動検出する。名刺の場合、会社名・部署・肩書き・氏名・住所・電話番号・メールアドレス等を自動認識し、分類する
(証拠2) 斜めから書類を撮影しても、正面から見たイメージに補正して保存できる
(証拠3) Evernote(クラウド上)に保存するほか、メールに添付することもカンタン
※上記の証拠1~3については、写真を付けた
ま、わりとベタな感じでまとめてみました。実は、10分ぐらいで片づけたので、超テキトーなんですけど・・・繰り返しになりますが、重要なことは、“宿題をする” ということです。ベタだろうが何だろうが、宿題をすることで、研修の導入がスムーズになったのは確かで、最後までそのノリを維持できたので、良かったと思っています。
金融業界における “デザイン・シンキング”
さて、“デザイン・シンキング” とは、一体何なのか? ネット上にもたくさんの解説がありますし、専門の書籍も出ています。このコラムで、それらを列挙しても仕方ないので、私なりの解釈を書いてみたいと思います。
デザイン・シンキングは、Human-Centered Design とも呼ばれます。要は、
“徹底的に顧客視点に立って、商品・サービスの開発を行う手法”
と言い換えられます。逆にいうと、これまでの開発手法が 顧客視点ではなかった からこそ、注目されているとも言えます。
例えば、私が専門とする金融業界において、昨年来 “FinTech(フィンテック)” というのが流行っています。 FinTech = Financial (金融) + Technology (技術、特にIT)を意味する造語なのですが、これを単に “金融IT” としてしまうと、非常に違和感がある。なぜなら、金融業界におけるITというのは、それこそ数十年前から存在しており、私などは、四半世紀の間、それを生業として生きてきたわけで、今さら金融ITと言われても、「だから、どうした!」という思いが先行してしまうのです。金融業界に身を置かれている方ならば、多少なりとも、この心情はご理解いただけると思います。
一方、金融業界に身を置かれていない、世の中の大多数のみなさんにとっては、金融ITは数十年前からあったのだ!と言われても、ピンとこないと思います。「金融機関って、どこにITを使ってんの?全然便利じゃないし!」というのが、主だった意見だと思います。
「これまで、銀行が世の中に提供した商品・サービスの中で、ITという観点でイノベーションと言えるのは、ATMしかない・・・」と言い切った政府高官がいたり、かのビル・ゲイツ氏などは、「今ある銀行は必要なくなる」ということを、1994年の段階でコメントしたりと、まぁ、金融ITに関する評価は、総じて低いものとなっています。
金融ITが評価されない最大の理由は、全く顧客視点ではないからなのだと思います。上述の通り、私は四半世紀の間、金融ITの世界に身を置いてきましたが、そのほとんどは、金融機関に勤務する人が使うシステムを作ることに費やしてきました。言い換えると、金融機関から見たお客様のためのシステムは、ほとんど作ってこなかったわけです。
以上を踏まえると、今般の “FinTech(フィンテック)” を私なりに定義すると、顧客視点に立った、顧客が使う金融ITとなります。
顧客視点に立った、顧客が使う金融ITと言われてしまうと、金融機関のIT部門や大手のITベンダーは、途方に暮れてしまいます。なぜなら、作ったことがないからです。どうやって作ればいいのかさえ、わからない。こういう背景・事情があって、FinTech関連のスタートアップやベンチャーが登場しているのです。そして、ベンチャーが使う開発方法論が、まさに、デザイン・シンキング というわけなんですね。
大企業における “デザイン・シンキング” の可能性
研修の中で、私は上記の見解を、参加者のみんなと共有しました。ま、わかりやすいたとえ話なので、みんなもふむふむと納得することしかり・・・。
「Takashi, very good ! However, ・・・」
講師からも評価のコメントがあったのですが、同時にツッコミも入りました。
「大企業 vs スタートアップ、ベンチャーという図式はわかりやすいんだが・・・、本当にそういう分類だけで説明していいのだろうか?大企業が 顧客視点に立って、デザイン・シンキングを取り入れるためには、どうしたらいいのだろう?次は、この点について議論してみよう!」
・・・また、難しいことを言い出したぞ、このおっさん・・・、ということで、この続きは、次回のお楽しみといたしましょう。
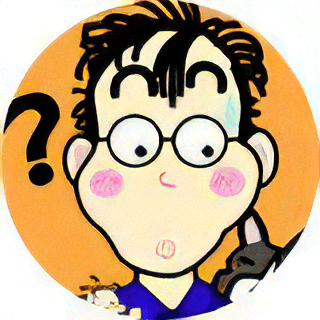
奈良タカシ
1968年7月 奈良県生まれ。
大学卒業後、某大手銀行に入行したものの、「愛想が悪く、顔がこわい」という理由から、お客様と接する仕事に就かせてもらえず、銀行システム部門のエンジニアとして社会人生活スタート。その後、マーケット部門に異動。金利デリバティブのトレーダーとして、外資系銀行への出向も経験。銀行の海外撤退に伴い退職し、外資系コンサルティング会社に入社。10年前に同業のライバル企業に転職し、現在に至る ( 外資系2社目 )。肩書きは、パートナー(役員クラス)。 昨年、うつ病にて半年の休職に至るも、奇跡の復活を遂げる。
みなさん、こんにちは ! 奈良タカシです。あさ出版より『外資流 ! 「タカシの外資系物語」』という本が出版されています。
出版のお話をいただいた当初は、ダイジョブのコラムを編集して掲載すればいいんだろう ・・・ などと安易に考えていたのですが、編集のご担当がそりゃもう厳しい方でして、「半分以上は書き下ろしじゃ ! 」なんて条件が出されたものですから、ヒィヒィ泣きながら(T-T)執筆していました。
結果的には、半分が書き下ろし、すでにコラムとして発表している残りの分についても、発表後にいただいた意見や質問を踏まえ、大幅に加筆・修正しています。 ま、そんな苦労 ( ? ) の甲斐あって、外資系企業に対する自分の考え方を体系化できたと満足しています。
書店にてお手にとっていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
奈良タカシ
![外資系・グローバル企業の転職・求人情報サイト [Daijob.com]](https://www.daijob.com/wp-content/themes/daijob-wp/assets/images/header_logo.svg)


