Global Career Guide


- 外資系転職求人 Daijob.com TOP
- Global Career Guide
- タカシの外資系物語
- 外資系タカシ流! 人前で話すときに気をつけていること (その1)
外資系タカシ流! 人前で話すときに気をつけていること (その1)
東京の人は早口だから、何を言っているのかわからない?!
みなさんは、自分の話し言葉に対して、何か “こだわり” のようなものを持っていますか?
私の場合、コンサルタントという職業柄、一般のビジネスパーソンと比較すると、人前で話をする機会が多い方だと思います。ま、元々人前で話したいがために、この仕事をやっていると言っても過言ではない。人前で話すという仕事が心底好きだし、それなりに誇りや自信も持っています。
相手の目を見て、ゆっくりと、噛まずに、わかりやすく話す・・・ 当たり前の話なのですが、実はできていない人、それも有名人に結構多い。一時、一世を風靡した、経済評論家のK女史の講演を聴講したことがあるのですが、話の内容以前に、早口で、専門用語(というか、流行りのスラング、バズワードのたぐい)を畳み掛けるように話されるので、何を言っているのか、さっぱりわかりませんでした。K女史だけでなく、最近パッと出の知識人(というか、タレント)には、こういう人が多いように思います。
私は関西出身なので、そもそも東京の人が早口に感じるというのは、潜在的な感覚としてあります。小学生の頃、漫才ブームで多くのスターが誕生しましたが、東京のセントルイスやツービートの漫才は、確かに早口すぎて、ついていくのに一苦労でした。しかし、独りよがりで何を言っているのかわからないわけではなかったので、上述のパッと出の知識人風タレントとは比較になりません。セントルイスも、ツービートも、プロの話術なんですよね、やっぱり・・・
私がこれまでの生涯で、最もわかりやすい話し方をされたのは、私にとっては同業の大先輩である 大前研一さん です。もちろん、大前さんは漫才をされるわけではないので、相当難しい話をされるわけです。でも、わかりやすい! あれなら、田舎にいる私の母親でも理解できるかもしれません。
話をわかりやすく構成していることに加え、ゆっくりと、相手のペースに合わせて(というか、相手のペース以下で)、ときにユーモアを交えながら話す。一対一で大前さんに話をされたら、コンサル料払っちゃおうかなー(かなり高いけど・・・)、という気になった社長が続出したのも納得です。私自身も、非常に学ぶところが多い、尊敬すべき先輩のお一人です。
タカシ流! 人前で話す際の5つのポイント
相手の目を見て、ゆっくりと、噛まずに、わかりやすく話す・・・ こと以外に、私が気を付けていること、それは、以下の5点です。
(1) 略語を使わない
(2) (日本語で同じ意味の言葉が存在する場合は)横文字、つまり 英語 を使わない
(3) 意識的に “間(ま)” を空ける
(4) 自分が100%理解していることしか話さない
(5) 事前に十分な練習を積むとともに、十分に休養をとって、話す体力を温存しておく
これら5つのポイント、すごく日本人的な(=非外資系的な)感じがしますよね。 特に、「(1) 略語を使わない」 なんて、外資ではありえないような気がしませんか? いや、でも違うんです。外国人というのは、思いのほか、略語を使いません。
例えば、ITの世界では、Supply Chain Management を 「SCM」、Data WareHousing を 「DWH」・・・ などといって、略す人が多い、というか、日本人ならほとんどの人が、略して話すでしょう。
一方、外国人の場合、7:3で略さない人の方が多いと思います。なぜか? おそらく、日本人の場合は、略した方が単に “楽” だからではないかと思います。英語が母国語の人にとっては、Supply Chain Management と言おうが、SCM と言おうが、そう大差はない。しかし、日本人にとっては、SCMの方がはるかに楽です。だから、日本人はSCMを多用するように思います。あと、ちょっとカッコいい響きがありますからね。
このことに関して、面白いエピソードがあるので披露しましょう。今を遡ること十数年前、前職のコンサルティング会社にTさんという大先輩がおりまして、彼の専門は、「ソフトウェア構成管理」 = Software Configuration Management 、略して “SCM” というものでした(ソフトウェア – ITが苦手な方は、アプリだと思ってください – のバージョン管理をする手法です。一昔前、WindowsとOfficeのバージョンが合わなくて、PCがうまく動作しない経験をされた方も多いのではないでしょうか。それです。今となっては、OSないしはアプリが自分でバージョンを調整してくれるので、ユーザーが気にする必要はほとんどなくなりましたが・・・。昔は結構大変だったんですよ、バージョン管理って。今でも、企業のホストシステムなんかでは、情報システム部さんあたりが、四苦八苦されているはずです・・・)。
ちょうどその時期、Supply Chain Management (こちらも略して “SCM”)という概念がアメリカからやって来まして、その解説本は、軒並みビジネス書のベストセラーになっていました。“SCM” と名がつけば、まず間違いなく、数万部は売れたのです。
Tさんの完全犯罪、その “動機” は?
さて、くだんのTさん、一体何をしたか? 懸命な読者のみなさんなら、もうだいたいわかりますよねぇ・・・ そう、もう1つの “SCM” をタイトルに冠した本を出したんです! タイトルは、『だれでもわかるSCM』 そりゃ売れますよね、なんたって、難解だと思われていた SCM が、“だれでもわかる” んですから(ただし、Supply Chain Managementではなくて、Software Configuration Managementなんですけど・・・)。
結果、Tさんの本は、八重洲ブックセンターのビジネス書部門で、5位(!)にランキングされました。確かに、Software Configuration Managementも重要ですが、分野としては、相当ニッチなんですよ! それが、日本有数の書店で、5位ってアンタ・・・ なんとTさんは、通勤時の往復にグリーン車を使って、その本を電車内で2週間余りで書き上げたそうですから、“SCM” ブームに乗り遅れないための、計画的な “犯行” ? だったのかもしれません。 いや、Tさんはものすごくペーソスの効いた方なので、日本人がわけのわからない略語に、批判なく飛びつくという “愚行” に対して、警鐘を鳴らしたのかも・・・ 実は今でも、Tさんとは年賀状のやり取りをしています。いつか、ことの真相を尋ねたいと思います。
少し話が脇にそれてしまいました。私が人前で話をするときに気をつけていることの1つめは、「(1) 略語を使わない」ということです。略語は耳障りがいいですが、Tさんの犯行のように、意味を取り違える可能性があり、かつ、わかったような気にさせてしまう(聞き手を煙に巻く)厄介なものなんです。だから、面倒でも略さずに、言葉の意味を、話し手・聞き手相互に認識しながら話すようにしています。
次回は、「(2) (日本語で同じ意味の言葉が存在する場合は)横文字 = 英語 を使わない」についてお話することにいたしましょう。
次回へ続く
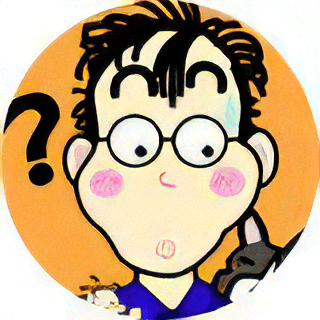
奈良タカシ
1968年7月 奈良県生まれ。
大学卒業後、某大手銀行に入行したものの、「愛想が悪く、顔がこわい」という理由から、お客様と接する仕事に就かせてもらえず、銀行システム部門のエンジニアとして社会人生活スタート。その後、マーケット部門に異動。金利デリバティブのトレーダーとして、外資系銀行への出向も経験。銀行の海外撤退に伴い退職し、外資系コンサルティング会社に入社。10年前に同業のライバル企業に転職し、現在に至る ( 外資系2社目 )。肩書きは、パートナー(役員クラス)。 昨年、うつ病にて半年の休職に至るも、奇跡の復活を遂げる。
みなさん、こんにちは ! 奈良タカシです。あさ出版より『外資流 ! 「タカシの外資系物語」』という本が出版されています。
出版のお話をいただいた当初は、ダイジョブのコラムを編集して掲載すればいいんだろう ・・・ などと安易に考えていたのですが、編集のご担当がそりゃもう厳しい方でして、「半分以上は書き下ろしじゃ ! 」なんて条件が出されたものですから、ヒィヒィ泣きながら(T-T)執筆していました。
結果的には、半分が書き下ろし、すでにコラムとして発表している残りの分についても、発表後にいただいた意見や質問を踏まえ、大幅に加筆・修正しています。 ま、そんな苦労 ( ? ) の甲斐あって、外資系企業に対する自分の考え方を体系化できたと満足しています。
書店にてお手にとっていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
奈良タカシ
![外資系・グローバル企業の転職・求人情報サイト [Daijob.com]](https://www.daijob.com/wp-content/themes/daijob-wp/assets/images/header_logo.svg)


