Global Career Guide


- 外資系転職求人 Daijob.com TOP
- Global Career Guide
- タカシの外資系物語
- シンガポール出張顛末記(その6)
シンガポール出張顛末記(その6)

欧米プロジェクトの経験者は?!
(前回の続き)転職後、最初のプロジェクトは、なんと海外!シンガポールに集まったメンバーは、国際色豊かで、多士済々のメンバー達。果たして、責任者であるタカシは、強者どもをコントロールすることができるのでしょうか・・・?!
今回のプロジェクト、あまり詳しくはお伝えできないのですが、一部にAI(Artificial Intelligence:人工知能)の技術を活用した最先端のものでして、私自身、経験がない!一方、欧米ではいくつかの事例があるため、欧米プロジェクトを経験したスタッフを招聘することにしました。
さて、どこの国のスタッフが来たと思いますか?!欧米人ではないんですねぇ、これが・・・。欧米プロジェクトの経験者、エキスパートを招聘・・・、という話になると、やってくるのは8割方インド人です。今回のように、AIなどの最先端技術になると、ほぼ100%の確率でインド人を招聘することになります。
AIなどの最先端IT技術は、インド人!なぜなら、インド人は数学が得意だから!!・・・ま、そうなんですけど、これではあまりにも短絡的というか、ステレオタイプにすぎます。なぜ、IT等先端技術のエキスパートを招聘すると、決まってインド人がやってくるのか?それは、インドに技術者を集約するセンター機能があるから、なのです。
インドには多くのIT技術者がいます。10年ほど前までは、欧米や日本との人件費差を活かして、設計は欧米日、開発はインド といった分業をすることで、より低コストの開発体制を作っていました(これを、オフショア開発といいます)。しかし最近では、人件費差もほとんどなくなり、また、インド側の技術力が完全に欧米日を凌駕する分野が多くなってきました。このような経緯を経て、インドに最先端技術の人的リソース、ノウハウが蓄積されていきました。結果、世界中のプロジェクトが、インド人をエキスパートとして招聘することになったとういわけです。
プロジェクトがうまく回る要素とは?!
私のチームは、以下のような構成になっています。
・ プロジェクトマネージャー = フランス人1名
・ スタッフ = 日本人3名、シンガポール人3名、中国人2名、インド人2名
・ 技術アドバイザー = インド人1名
ご覧の通り、技術アドバイザーの1名を含め、3名のインド人が参画してくれています。彼ら・彼女らの技術力や知見は素晴らしく、参加メンバー全員が、目を見張るようなものばかり。さすが、インド人!
インド人が参画するプロジェクトには、特定の顕著な傾向が見られます。それは、
インド人を中心にプロジェクトが回っていく
ということ。ま、卓越した技術力を持っているのですから、そうなるのもわかります。一方で、プロジェクトは、技術的な知見のみで進んでいくわけではない。実際には、クライアントとの関係、プロジェクト内メンバー同士の関係、ステークホルダーとの関係等々、人間関係の良否が結果に大きく影響します。
これは私の経験則ですが、“社交性” という観点では、インド人はそれほど強くはない(ま、日本人は、もっと強くないんですが・・・)。よって、インド人のみを中心にプロジェクトを回してしまうと、ときに、人間関係がギクシャクするケースが見られるので、注意を要します。インド人の能力を最大限に活かしつつ、彼ら・彼女らが浮いてしまわないチームをどうやって作るのか、責任者としての、私の腕の見せ所というわけです。
インクルージョンとは、何か?!
ここ最近、ダイバーシティ(Diversity)という言葉が一般的になってきました。日経連の定義によると、ダイバーシティというのは、以下の通り定義されます。
【ダイバーシティとは?】
異なる属性(性別、年齢、国籍など)や従来から企業内や日本社会において主流をなしてきたものと異なる発想や価値を認め、それらを活かすことで、ビジネス環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し利益の拡大につなげようとする経営戦略。
日本の場合、ダイバーシティが注目されるにいたった最初のトリガーは、女性活躍推進にあったと思います。そこから、障がい者やGLBTなどに展開していきました。結果、女性・ハンディキャップのある方・性的嗜好の違う方を、差別しないという意識は、まだまだ十分ではありませんが、それなりに醸成されてきたように思います。
一方で、日本社会に足りないのは、「差別しない」の次、
「異なる個性をどう活かすか?」の具体策
だと思います。これを強調したい場合、ダイバーシティに加え、インクルージョン(Inclusion)という言葉を使うことがあります。外資系企業の場合、Diversity & Inclusion という、2語1セットで表現されることが多い。
これは私の私見ですが、ダイバーシティとインクルージョンには、以下のようなニュアンスの違いがあるように思います。
○ ダイバーシティ = 異なる個性の融合
○ インクルージョン = 異なる個性を融合し、個性を発揮する
日本において、インクルージョンまで踏み込めない最大の理由は、結局は、その多くが単一民族内での話で終わるからなのだと思います。そもそも個性の発揮を重視しない国民性ですから、差別を失くして融合すれば、それでOK。みんな仲良くやりましょう!そんな感じです。
一方、グローバル社会においては、前述のインド人技術者のように、多民族が前提となります。多民族の融合には、それなりのコストがかかります。そして、そのコストを上回るリターンを得るためには、ダイバーシティによって成果を上げるインクルージョンにまで高めないと、意味がないわけですね。
私の担当するプロジェクトに参画してくれた、インド人メンバーのみなさん。当初は固かった表情が、最近は明るくなってきました。私も、すでにもう2回もランチを一緒に取っています(いずれも、めっちゃ辛いカレー屋さんでしたが・・・)。 ダイバーシティを超えた、インクルージョン目指して、頑張っていきたいと思います!
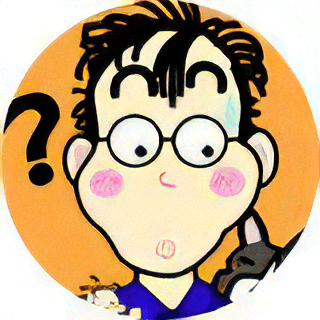
奈良タカシ
1968年7月 奈良県生まれ。
大学卒業後、某大手銀行に入行したものの、「愛想が悪く、顔がこわい」という理由から、お客様と接する仕事に就かせてもらえず、銀行システム部門のエンジニアとして社会人生活スタート。その後、マーケット部門に異動。金利デリバティブのトレーダーとして、外資系銀行への出向も経験。銀行の海外撤退に伴い退職し、外資系コンサルティング会社に入社。10年前に同業のライバル企業に転職し、現在に至る ( 外資系2社目 )。肩書きは、パートナー(役員クラス)。 昨年、うつ病にて半年の休職に至るも、奇跡の復活を遂げる。
みなさん、こんにちは ! 奈良タカシです。あさ出版より『外資流 ! 「タカシの外資系物語」』という本が出版されています。
出版のお話をいただいた当初は、ダイジョブのコラムを編集して掲載すればいいんだろう ・・・ などと安易に考えていたのですが、編集のご担当がそりゃもう厳しい方でして、「半分以上は書き下ろしじゃ ! 」なんて条件が出されたものですから、ヒィヒィ泣きながら(T-T)執筆していました。
結果的には、半分が書き下ろし、すでにコラムとして発表している残りの分についても、発表後にいただいた意見や質問を踏まえ、大幅に加筆・修正しています。 ま、そんな苦労 ( ? ) の甲斐あって、外資系企業に対する自分の考え方を体系化できたと満足しています。
書店にてお手にとっていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
奈良タカシ
![外資系・グローバル企業の転職・求人情報サイト [Daijob.com]](https://www.daijob.com/wp-content/themes/daijob-wp/assets/images/header_logo.svg)


