Global Career Guide


- 外資系転職求人 Daijob.com TOP
- Global Career Guide
- タカシの外資系物語
- 外資系企業における人事採用最前線(その5)
外資系企業における人事採用最前線(その5)

外国人には “エントリーシート” が通じない?!
(前回の続き)外資系企業における採用担当者は、エントリーシートをどのように見ているのか? 日系と外資では、エントリーシートの見方が違う?! 以下、その違いをお話しすることにいたしましょう。
そもそも、エントリーシート(Entry Sheet)というのは、和製英語です。 “ES” と略して、さも “昔から英語の世界でありまんねん” 的に表現されているので誤解しがちなのですが、外国人に Entry Sheet と言っても、何のことなのか、全く通じないと思います。
日本の Entry Sheet に該当するのは、英語では、job application または application form といいます。志望者のことは applicant といいまして、私はこの言葉を聞くと、映画 『ブレード・ランナー』 の “レプリカント” を想像してしまって、面接時に志願者が急にロボットに化けて、私を襲ってくるんではないかと、いつも冷や冷やしながら面接しています。映画にもそういうシーンあるし・・・(わかる人だけ笑ってください・・・)。
日本の Entry Sheet と英語の application form、この2つの言葉、英語的な “語感” が相当違います。 “entry” “apply” とも、日本語に訳すと -申し込む- という意味なのですが、それぞれ、以下のような使われ方をします。
- “entry” ・・・ ある応募対象に、何となく、漠然と申し込んだ、という感じ。懸賞に応募した、ECサイトの割引クーポン券を申し込んだ、そんな感じです
- “apply” ・・・ その応募対象に、強い意思を持って、「是非私を採用してください!」的なノリで、応募した、という感じ。学校や仕事に対して使われることが多い一方、懸賞の応募に対して、この言葉が使われることは、まずありません
上記の違いは、日系と外資におけるエントリーシートの考え方の違いを大いに示唆しています。日系企業におけるエントリーシートというのは、「受付表」「整理表」の位置付けでしかない。もちろん、記載要件(書き方のルール)を満たした上で、目立つ内容が記載されている方が望ましいのは確かです。しかし、あくまでも 「受付表」 なのですから、平均的に書かれていれば それでOK、だからコピペが容認(!)されているのです。
日系企業の人事担当者もバカではないので、多くのエントリーシートがコピペされていることぐらい、百も承知です。でも、それを取り立てて問題視しない。なぜか? 議論の本質ではないからです。だって、「受付表」なのですから、その巧拙を議論するような話ではないのです。
外資がエントリーシートに求めるもの
一方、外資系企業におけるエントリーシートというのは、“apply” ですから、強い意思を持って、「是非私を採用してください!」的なノリがあるかどうか、確認するための手段の1つとなります。よって、コピペ多用のしょうもないエントリーシートは、その段階で落とします。この応募者と会いたい! と思える、“光る何か” がなければ、エントリーシートの段階で落ちるのです。だから、気合を入れて書かないといけないというわけ。
もちろん、外資においても、何の変哲もない、平均的なエントリーシートが通ってしまうケースもあります。それは、その外資系企業の経営戦略上、「今すぐに人が欲しい!」という場合です。外資の場合は、この手の “季節限定的な” 採用が結構多い。運が良ければ、コピペのエントリーシートでも採用されることは、ままあります。
しかし! 運任せで応募するというのは、“entry” です。外資の “apply” を満たすためには、“光る何か” がほしい。以下で、その一例を示したいと思います。まずはよくある、コピペ系、キラキラの経歴羅列系の記載から。
【よくあるエントリーシート】
「ゼミではマーケティングにおける人工知能の活用を研究し、文系ですがプログラミング講座の単位も取得しました。サークルではラクロス部の副キャプテンをやって、インカレで入賞も果たしました。ボランティアにも参加し、週末のたびに地方に行くこともしばしば。今後はグローバルに視野を向けて、社会を変革するために、御社のようなグローバルベースでのコンサルティングファームを志望していますっ! キラッ、キラ☆」
日系の “entry” なら、これでOKです。正直、“光る何か” は全く感じませんが、平均レベルではあるので、「はいはい、OK!」てな感じで、面接に回されるパターンです。一方、外資の “apply” 基準からすると、かなり弱いです。なぜでしょうか?
“光る” のは過去の “事実” ではなく・・・?!
外資系企業の人事担当者および採用の決裁権限を持つ役員層の観点から、上記エントリーシートを解析してみると、以下のような評価となります。
(1)事実の羅列である
(2)各事実に関連性がない
(3)志望動機がなぜ導出されたか、わからない
ダラダラ~っと美辞麗句が並んでいるのですが、それぞれの関連性が全く見えません。これではダメ! “光る何か” というのは、各事実のキラキラ度合いではない! 人工知能とか、ラクロス部でインカレ入賞とか、地方でボランティアとか、そういうのが光るのではありません。
【“光る” エントリーシート】
「ゼミではマーケティングにおける人工知能の活用を研究しましたが、実用化のためには、いくつかのハードルが存在すると思います。実務と人工知能で多くの実績を持つ御社において、課題解決のフロントに立ちたいと思います・・・」
「地方のボランティアに参加して、多数のステークホルダーの考えをまとめ、プログラムを推進していく事務局が必要だと痛感しました。企業および社会に対して、プログラム・オフィスのサービスを提供している御社において、日本や世界の組織変革に携わっていきたいと希望します・・・」
要するに、
「事実は、自分がアピールしたいこと=志望動機のダシ として使う」
ということです。これが、大原則。にもかかわらず、多くの人は、「事実そのもの」でアピールしたがる傾向にある。実は、この手法では全く光らないのです。
また、事実は志望動機のダシでしかないので、そんなにキラキラしていなくも構わない。例えば、
「学生時代は勉強が基本の毎日でしたが、本はたくさん読みました。〇〇という本に書かれていた△△に共感し、調べていくうちに、御社の事業にたどりつきました・・・」
というのでもアリです。
いかがでしょうか? キラキラ輝くのは、過去ではなく、未来です。エントリーシートに一味加えて、外資でも通用する、application form に仕上げてみましょう。学生諸君の検討を期待しています。体に気を付けて、シューカツ、頑張って下さいね! では!!
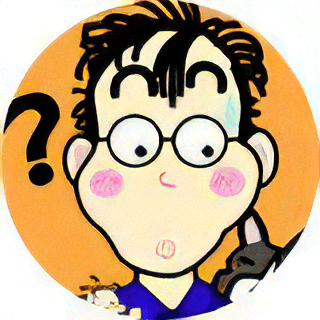
奈良タカシ
1968年7月 奈良県生まれ。
大学卒業後、某大手銀行に入行したものの、「愛想が悪く、顔がこわい」という理由から、お客様と接する仕事に就かせてもらえず、銀行システム部門のエンジニアとして社会人生活スタート。その後、マーケット部門に異動。金利デリバティブのトレーダーとして、外資系銀行への出向も経験。銀行の海外撤退に伴い退職し、外資系コンサルティング会社に入社。10年前に同業のライバル企業に転職し、現在に至る ( 外資系2社目 )。肩書きは、パートナー(役員クラス)。 昨年、うつ病にて半年の休職に至るも、奇跡の復活を遂げる。
みなさん、こんにちは ! 奈良タカシです。あさ出版より『外資流 ! 「タカシの外資系物語」』という本が出版されています。
出版のお話をいただいた当初は、ダイジョブのコラムを編集して掲載すればいいんだろう ・・・ などと安易に考えていたのですが、編集のご担当がそりゃもう厳しい方でして、「半分以上は書き下ろしじゃ ! 」なんて条件が出されたものですから、ヒィヒィ泣きながら(T-T)執筆していました。
結果的には、半分が書き下ろし、すでにコラムとして発表している残りの分についても、発表後にいただいた意見や質問を踏まえ、大幅に加筆・修正しています。 ま、そんな苦労 ( ? ) の甲斐あって、外資系企業に対する自分の考え方を体系化できたと満足しています。
書店にてお手にとっていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
奈良タカシ
![外資系・グローバル企業の転職・求人情報サイト [Daijob.com]](https://www.daijob.com/wp-content/themes/daijob-wp/assets/images/header_logo.svg)


