Global Career Guide


- 外資系転職求人 Daijob.com TOP
- Global Career Guide
- タカシの外資系物語
- タカシの “転職はツラいよ!” (その5)
タカシの “転職はツラいよ!” (その5)

契約が “曖昧” に感じる理由とは?!
(前回の続き)A社への転職が内定したタカシに、大きく立ちふさがった “壁”、それは、現勤務先との契約事項でした。さて、タカシはいかにしてこの難局を乗り越えたのでしょうか?
前回のコラムでもお話しした通り、現勤務先において、私がパートナー昇進時に交わした契約内容は、以下の通りでした。
(パートナー昇進後、他社への転職に際しては・・・)
① “報償” の放棄
② 特定クライアントへの “出入り禁止”
③ “競合先” には転職しない
これらの事項を、すべて “文字通りに” 解釈すると、転職そのものが非常に困難になる、というか、実質不可能になってしまいます。すごく本質的なことを言えば、憲法において 「職業選択の自由」 が保障されている以上、あまりにも無茶な取り決めは、それ自体の実効性が問われます。では、どう考えるのか?
上記の取り決めに、何となく違和感を感じる最大の理由は、表現が極めて抽象的で、曖昧だからです。定量的な表現ではない、と言ってもいいでしょう。
では、具体的・定量的な表現を用いた記述とは、どのようなものか? 以下の例をご覧ください(※なお、以下の記載は、あくまでも例示であって、フィクションです)。
① “報償” の放棄 = stock option 無効、RSU (Restricted Stock Units)における unvested 分無効
② 特定クライアントへの “出入り禁止” = 過去1年間において、実際にFEEをもらっていたクライアントを対象とする
③ “競合先” には転職しない = 退職時点において、会社が定義する “競合先” に転職する場合、上記②の条件+αの制限を受ける
タカシのデリバティブ講座
少し解説しましょう。まず、①について、ここでいう “報償” とは、ほとんどの場合、“株式” を指します。ご存知の通り、ストック・オプションというのは、事前に決められた価格で、株式を購入する “権利” のことです。例えば、2年後に100円で株式を購入できるストック・オプションの場合、2年後の実際の株価が120円になっていれば、差額分の20円が儲かる、という代物です。逆に、2年後の実際の株価が80円だった場合は、このストック・オプションに価値はありません。
ストック・オプションが機能するのは、ベンチャーやスタートアップ企業にほぼ限定されます。なぜなら、上場済の大手企業の場合、株価のボラティリティ(変動)があまり大きくないため、“報償”としての魅力がないためです。逆に、ベンチャー企業の場合、ボラティティがあまりにも大きいため、超がつく億万長者が誕生するわけですが・・・。
(※ ちなみに、金融取引におけるオプション取引には、購入する権利も売却する権利も、両方含まれます。もっというと、“購入する権利”を購入する権利、その権利を購入する権利・・・と、いくらでもバリエーションが作れます。これらが典型的なデリバティブという金融商品であって、オリジナルの株式から派生して、何十倍、何百倍もの金額が、取引されることとなります。リーマンショックの主要因は、サブプライム層という信用のない階層に住宅ローンを販売したことがきっかけにはなっていますが、そこにオプション取引が絡んで、ありえないような金額に膨らんでしまったことの方が、実体経済に与えた影響は大きいことを忘れてはいけないでしょう・・・)
アメリカ資本の大手企業の場合、RSU (Restricted Stock Units)という制度を活用しているケースが多いと思います。これは、ストック・オプションではなく、株式の現物そのものなのですが、多くの場合、“報償” が与えられた時点よりも将来において、また、複数年度に分割して渡されます。
- ● RSU の例・・・「3年後から500円の株を毎年100円ずつ5年かけて渡す」としたケースにおいて、その4年後はどうなっているか、というと・・・
- 3年後末 100円、4年後末 100円 支払済 この株式を vested stock という
- 5年後末 100円、6年後末 100円、 7年後末 100円 未払 この株式を unvested stock という
さて、“報償” の放棄という場合、RSUのどの部分が対象となるのでしょうか?
外資のサラリーが日系よりも高く見えるカラクリとは?!
RSUの期間中に他社に転職した場合、まず unvested stock は間違いなく無効になると思います。これについては、論理的に理解しやすいでしょう。では、vested 分はどうなるか?
vested の対応については、ケースバイケース だと思います。すでに支払われたものを返却するというのは、一見すると合点がいかないと思います。しかし!RSUの成り立ち、性質を考慮すると、「それもやむなし・・・」と思えてきます。
そもそもRSUというのは、「その対象者が、中長期にわたり会社にメリットを与えてくれること」を期待したものです。よって、支払いの総額は、株主総会の議決事項として、会社の持ち主である株主が決めています。実は、みなさんがもらっている ボーナス(賞与)も同じ性質のものなのです。
日本人の多くは、ボーナスというのは、過去1年間に実現した成果について与えられていると勘違いしています。“お疲れ様で賞!” みたいな感じですね。しかし、残念ながら、これは大いなる誤解です。
ボーナスというのは、将来において、これまでと同様に頑張ってね! 期待してるよ!という意味で、「未実現の期待成果について、仮に先払いされているもの」なのです。だから、転職することで期待を裏切ったと判断されたら、返せ、オラー!!(怒)と言われても仕方ないものなんですね。
実際に、過去において、私は支払済のボーナスを、その半年後に返却したことがあります。そのときは、憤懣やるかたなしと感じたのですが、外資に慣れてくると、そういうもんだと思えるようになってきました。
「ボーナス返せ!」は、日系企業においても、株式会社組織であれば起こりえます。しかし日本では、そういうことは、まず起こりません、なぜか?
その理由は、わかりやすく言うと、
「ボーナスとして払えなくもないのだが、返せ!となるのを恐れて、払っていない」
からです。つまり、将来を悲観的にみて、ボーナスとして払える分を、内部留保として蓄積しているのです。一方、外資は太っ腹に、払い切ります(ま、そうしないと、社員が次々に辞めてしまうからですが・・・)。
私は、外資系企業の給料が、日系企業に比べると高いと思われている部分の多くは、この影響が大きいと考えています。外資は、払える部分は惜しみなく払うが、返却を要求されることもあるし、もっと酷いと解雇されることもある。一方で、日系は十分に支払われているわけではないが、返却を要求されることはまずないし、解雇のリスクも低い、ということではないでしょうか。つまり、リスクまで考慮すると、どちらも同じなのです。
で、転職に際し、私の RSU はどうなったのか・・・?それは、みなさんの想像にお任せします。ま、トホホ・・・(T-T)とだけ、言っておきましょう。マジ、トホホ・・・(T-T)(T-T)
次回の最終回にて、②③についてはお話しし、このシリーズを締めたいと思います。では!
(次回続く)
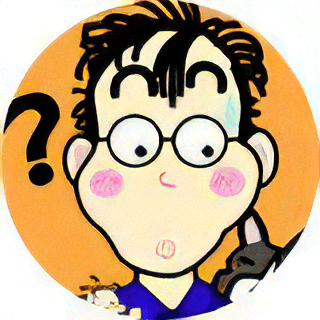
奈良タカシ
1968年7月 奈良県生まれ。
大学卒業後、某大手銀行に入行したものの、「愛想が悪く、顔がこわい」という理由から、お客様と接する仕事に就かせてもらえず、銀行システム部門のエンジニアとして社会人生活スタート。その後、マーケット部門に異動。金利デリバティブのトレーダーとして、外資系銀行への出向も経験。銀行の海外撤退に伴い退職し、外資系コンサルティング会社に入社。10年前に同業のライバル企業に転職し、現在に至る ( 外資系2社目 )。肩書きは、パートナー(役員クラス)。 昨年、うつ病にて半年の休職に至るも、奇跡の復活を遂げる。
みなさん、こんにちは ! 奈良タカシです。あさ出版より『外資流 ! 「タカシの外資系物語」』という本が出版されています。
出版のお話をいただいた当初は、ダイジョブのコラムを編集して掲載すればいいんだろう ・・・ などと安易に考えていたのですが、編集のご担当がそりゃもう厳しい方でして、「半分以上は書き下ろしじゃ ! 」なんて条件が出されたものですから、ヒィヒィ泣きながら(T-T)執筆していました。
結果的には、半分が書き下ろし、すでにコラムとして発表している残りの分についても、発表後にいただいた意見や質問を踏まえ、大幅に加筆・修正しています。 ま、そんな苦労 ( ? ) の甲斐あって、外資系企業に対する自分の考え方を体系化できたと満足しています。
書店にてお手にとっていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
奈良タカシ
![外資系・グローバル企業の転職・求人情報サイト [Daijob.com]](https://www.daijob.com/wp-content/themes/daijob-wp/assets/images/header_logo.svg)


