Global Career Guide


- 外資系転職求人 Daijob.com TOP
- Global Career Guide
- 有元美津世のGet Global!
- 厳格化される学生ビザ(2)–カナダ、オーストラリア
厳格化される学生ビザ(2)–カナダ、オーストラリア
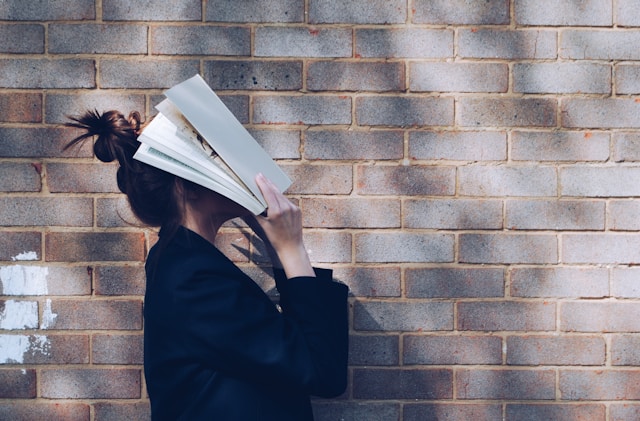
半年ほど前に、英語圏で相次いで学生ビザの発給条件が厳しくなっていることについて書きましたが、今回は、その後の進展について書きたいと思います。
カナダ
今年に入り、カナダ政府は、今後2年で学生ビザ発給数の35%削減を発表しましたが、2025年にはさらに10%削減し、かつ大学院生も含むことを決めています。
また、11月8日以降、14ヵ国の学生に対する学生ビザ優先(fast track)制度が廃止され、インド、パキスタン、ベトナム、フィリピンなど対象国で波紋を広げています。学生ビザ発給には、通常の手続きであれば数ヵ月かかるところが、同制度では1ヵ月ほどとかなり時短ができ、かつ発給率も高いところがメリットでした(ただし申請料が高い)。
日本は含まれていないので、直接関係はありませんが、対象国では、すでにカナダを避けてヨーロッパやオーストラリアを目指す学生も出てきており、それらの国での競争が激しくなる可能性があります。
こうした中、カナダでは、今秋、すでに新入生の数が昨年比3割減という大学も相次いでおり、それによる収入源で、講師やTA(teaching assistant)の採用を凍結する大学まで出てきています。オンタリオ州の公立大学20校からなる評議会では、学生ビザの発給数削減によって、同州では9億加ドル(1000億円近く)の収入損失になると見積もっています。
就労許可
11月1日からは、卒業後に得られる就労許可(PGWP=post-graduation work permit)の取得条件も変わりました。応募時に、IELTSなどの語学力テストの成績を提出し、定められたレベルを満たしていることが必要となります。
また、universityの学士・修士・博士課程を卒業していない場合(他の課程やcollegeを卒業した場合)、専攻分野が新たな条件として加わり、観光・ホスピタリティ、ビジネスなどの専攻では、就労許可を得られなくなりました。医療やSTEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)、農業などカナダで長期的に人材不足の5分野を専攻した学生は、最長3年の就労許可を得ることができます。
オーストラリア
学生ビザ発給数を2025年には(コロナ前の)27万人に減らす計画の豪政府ですが、現在、その法案が上院で審議中で、野党が反対しているため、法案が通過しない可能性が高まっています。といっても、最大野党は「さらなるカットが必要」ということで、16万人まで削減することを求めているのです。(が、審議中の法案が通らなければ削減は行われず、現状のままということになる)
もちろん、大半の大学も、この法案に反対しており、経済的に大きな打撃となるだけでなく、世界的にオーストラリアの評判を落とすものだと主張しています。トップ8校では、初年度だけで10億豪ドル(1000億円)の損失となり、一般経済にも53億豪ドル(5000億円異常)の損失、2万人の失業を招くことになるということです。
学生ビザ発給数が減ることから、すでにスタッフを減らしたり、留学生からの願書受付を減らしている大学もあります。
また、法案が通った場合、2025年1月からの施行となるため、2025年度分は、すでに規定の上限に達したので、願書受付を停止している大学もあります。
学生ビザ発給数は、個々の大学向けに割り当てられ、職業訓練(専門)学校で一番減少数が大きいようです。大学(university)では、都市部での減少数が大きく、住宅危機を抱える大都市での混雑を抑え、留学生らを地方に振り分けようという目論見です。(が、「地方の大学になど行きたくない」という留学生もおり、そうした学生は留学先を他の国に変えている)
すでに留学数減
オーストラリアでは、今年度(2023年10月~2024年4月)、すでに学生ビザ発給数が38%減少しました。国別では、一番減少したのは、フィリピン(67%減)、コロンビア(62%)、インド(56%)です。
とくに職業訓練学校(57%)や語学学校(50%)での減少が激しいですが、大学(university)でも25%減少しています。
この背景には、今年に入り、必要な英語力(IELTS)や留学資金(2万4000豪ドルが2万9000豪ドル)が引き上げられたことに加え、ビザ申請料の値上げ(710豪ドルが1600豪ドル)や卒業後の就労ビザ(Temporary Graduate Visa)の期間短縮があります。
ビジネスとしての高等教育
オーストラリアでは、教育部門が第4の輸出産業であり、一大産業を成しています。留学生は平均してオーストラリア人学生の倍近くの学費を払っており、たとえばシドニー大学では、留学生が収入全体の4割を占めています。こうした中、「学費に見合った品質の教育が提供されているのか」「金儲けに走りすぎではないか」という懸念もあります。
また、近年、留学生数が増える一方、オーストラリア人の学生は減っているため、専門学校なども含めた高等教育の学生に占める留学生の割合は、全体の3割に達しています。途中で退学する大学生の割合は、留学生(19%)よりオーストラリア人学生の方が高く(25%)、卒業する割合は61%に留まっており、オーストラリア人の大学離れも問題視されています。
日本へのインド人留学生に影響?
半年前に、アジアを目指す東南アジアの留学生についても書きましたが、英語圏への留学の門が狭まっていることから、インドのメディアでは「留学先として日本のトップ大学(東大、京大、東北大、阪大)も検討すべき」という記事も登場しています。日本では、とくにSTEM分野で、インドからの応募者が増えているそうです。
といっても、まだ2000人未満なので、中国からの留学生数とは桁が違います。インド駐日大使は、これを1~2年で倍に増やしたいそうですが、英語で受講できる授業が増えないと難しそうです。

有元美津世
大学卒業後、外資系企業勤務を経て渡米。MBA取得後、16年にわたり日米企業間の戦略提携コンサルティング業を営む。社員採用の経験を基に経営者、採用者の視点で就活アドバイス。現在は投資家として、投資家希望者のメンタリングを通じ、資産形成、人生設計を視野に入れたキャリアアドバイスも提供。在米30年の後、東南アジアをノマド中。訪問した国は70ヵ国以上。
著書に『英文履歴書の書き方Ver.3.0』『面接の英語』『プレゼンの英語』『ビジネスに対応 英語でソーシャルメディア』『英語でTwitter!』(ジャパンタイムズ)、『ロジカル・イングリッシュ』(ダイヤモンド)、『英語でもっとSNS!どんどん書き込む英語表現』(語研)など30冊。
![外資系・グローバル企業の転職・求人情報サイト [Daijob.com]](https://www.daijob.com/wp-content/themes/daijob-wp/assets/images/header_logo.svg)

